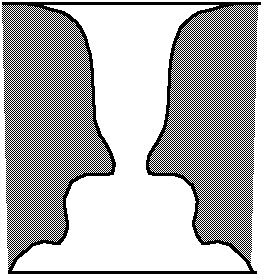意識と無意識の間
〜脳型計算機への挑戦〜
我々はよく、「意識がある」とか「無意識の内に」とかいう言葉を使うが、「意識」って何なのかちゃんと解っているのだろうか?また、意識を持った計算機、というのは作ることができるのだろうか?意識の研究の先駆者で脳型計算機の構築を目論む北海道大学
数学科津田一郎教授にインタビューを敢行した結果をお届けする。
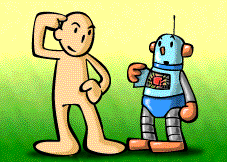 意識、というのは一体、何だろうか。人間にとって「意識」が一番大事だと皆思っているのではないだろうか。どんなに何かの能力が高い人間がいても「意識」を持っていなかったら、人間とは呼べないだろう。それは チェスの世界チャンピオンに勝てる計算機とか、絵画を創作できるコンピュータの様な「装置」に過ぎない。人間が人間たる最低限の条件は「意識」を持っていることだと思われている。
意識、というのは一体、何だろうか。人間にとって「意識」が一番大事だと皆思っているのではないだろうか。どんなに何かの能力が高い人間がいても「意識」を持っていなかったら、人間とは呼べないだろう。それは チェスの世界チャンピオンに勝てる計算機とか、絵画を創作できるコンピュータの様な「装置」に過ぎない。人間が人間たる最低限の条件は「意識」を持っていることだと思われている。
そう思われている割には、意識自体の研究は大変遅れている。実際、意識の研究なんて幽霊や超能力の研究と大差ないと思われていた時代はつい最近のことだ。だが、幽霊や超能力と異なって、「意識」はそれが存在しているのは明らかである。ただ、研究対象としてあまりにも漠然としていて何を研究したらいいのかあまりにもつかみどころが無かったに過ぎない。「意識」というのはあくまで人間の「大脳」という一個の「器官」の「機能」に過ぎない、と思うことによりようやく意識の研究が始まった。つまり、筋肉や血液を研究するのと同じように「大脳」を研究するわけだ。
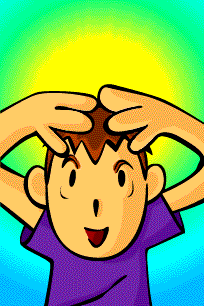 この様な行き方、つまり、「意識とは大脳と言う器官の機能の一つである」という考え方が主流になってきた背景は2つある。その第一は、 測定技術の進歩であり、また、もう一つは 権威ある研究者の参加である。そのおかげで、「意識」を研究すること自体は非常にメジャーな研究となったがその成果自体はお寒い限りだ。
この様な行き方、つまり、「意識とは大脳と言う器官の機能の一つである」という考え方が主流になってきた背景は2つある。その第一は、 測定技術の進歩であり、また、もう一つは 権威ある研究者の参加である。そのおかげで、「意識」を研究すること自体は非常にメジャーな研究となったがその成果自体はお寒い限りだ。
成果がお寒い限りなのにも理由が二つある。ひとつは 従来の科学の研究手法で大脳の研究をすることが大変難しい、ということ。もう一つは、 意識の定義が不明解であることだ。非常に多くの人が意識について研究している割には、合意の様なものがちっとも得られていない。
意識とは何だろうか?という定義自体から始める必要があるのではなかろうか。意識とは何か?人間の大脳とは結局、外界から受け入れた刺激を処理してどう行動すべきかを決める器官、ということができるだろう。実際、大脳には外界からの刺激を処理する部分と、思考を司る部分がある。だが、これだけでは、普通の計算機と変わらない。1と1を入れたら和の2を返す、というのと同じことだ。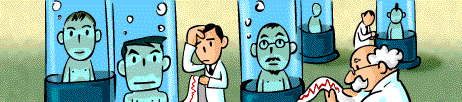
 計算機と人間の差は柔軟性にある。計算機は できないことはできないが 人間なら何とかしてしまうのだ。この秘密は「無意識」の存在にある。大脳は処理できないもの、矛盾を生じているものは全て「無意識」の世界に追いやってしまい、自分で処理できる部分だけを取り出して世界を構成している。この「都合良く取り出された理解できる部分だけの集合」が「意識」に他ならない。つまり、意識とは、外界からの「刺激」とそれを処理する「思考」の間に立ち、都合の良いものだけをフィルターにかけてえり分けている部分、ということになる。チェスができる計算機が作れるように「思考」を行なう計算機は作れるし、また、音声認識や郵便番号読み取り機に見られるように「刺激」の処理をする機械もつくれる。問題は「刺激」という入力と「思考」という処理機構をどうやってつなげるか、という部分だ。この部分を現在のコンピュータは欠いているがゆえに意識を持たず、決して人間の様には感じられない。
計算機と人間の差は柔軟性にある。計算機は できないことはできないが 人間なら何とかしてしまうのだ。この秘密は「無意識」の存在にある。大脳は処理できないもの、矛盾を生じているものは全て「無意識」の世界に追いやってしまい、自分で処理できる部分だけを取り出して世界を構成している。この「都合良く取り出された理解できる部分だけの集合」が「意識」に他ならない。つまり、意識とは、外界からの「刺激」とそれを処理する「思考」の間に立ち、都合の良いものだけをフィルターにかけてえり分けている部分、ということになる。チェスができる計算機が作れるように「思考」を行なう計算機は作れるし、また、音声認識や郵便番号読み取り機に見られるように「刺激」の処理をする機械もつくれる。問題は「刺激」という入力と「思考」という処理機構をどうやってつなげるか、という部分だ。この部分を現在のコンピュータは欠いているがゆえに意識を持たず、決して人間の様には感じられない。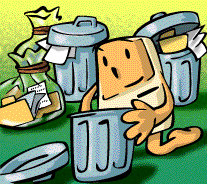
こう考えてくると、大脳にとって本当に大事なのは「無意識」の部分と言うことになる。いわゆる「ゴミ捨て場」に相当する「無意識」があるからこそ、人間は「意識」を維持できるわけだ。そういう意味では、人間の大脳の機能を模倣する計算機を作るには「無意識」を持った計算機をつくることこそ大切だと言うことになる。言い代えれば、人間の本質は「意識」でなく、「無意識」にある。脳型計算機を作る理由も実はそこにある。現在のところ「意識」をつくるアルゴリズムを研究しているに過ぎないが、「意識」をもつ計算機を作る過程で「無意識」の作り方はおのずと見えてくるだろう。「ゴミ捨て場」たる無意識を持たなければ「意識」は作れないからだ。無意識を持った計算機、それが登場した時、初めて、我々は人間の意識とは何かを理解できるのかも知れない。
津田一郎氏
1977年大阪大学物理学科卒、1982年京都大学物理学科で理学博士号取得。その後、新技術事業団などを経て、1988年九州工業大学情報工学部知能情報科学科助教授。1993年より現職
測定技術の進歩
脳、というのは運動しない器官である。つまり、見た目上の変化が何もない。これが他の器官、例えば心臓を研究するなら、鼓動の状態をモニターしていれば心臓の研究をすることが出来るわけだが、脳の場合、何かが動くわけではないから変化が解らない。これでは、「意識」を大脳の「機能」として研究しようにもやりようが無かった。ところが、最近、 PETやMRIといった外部から脳の状態を直接に観測できる装置が開発された。つまり、「意識」と大脳の「機能」を関係づける術が見つかったわけだ。意識を大脳の機能としてとらえようという研究が立ち上がり得たのもこういう測定技術の進歩が大きいのだ。
PETやMRI
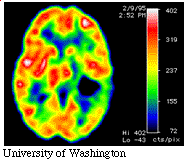 PETはPositron Emission Tomographyの略。これを使うと脳のどの部分が活動しているかを知ることが出来る。もともとは医学的に脳の異常を知るために医学的に開発された観測機器だが、これを用いて、人間の意識状態と脳の活動状態を関係づけることが出来るようになった。目を使っている時に活動しているところが視覚を司っている、などということが直接的に観測できるようになったわけで、この価値は大きい。解像度もかなり高いので、脳の活動状態と人間の意識を詳しく関係づけられる。
PETはPositron Emission Tomographyの略。これを使うと脳のどの部分が活動しているかを知ることが出来る。もともとは医学的に脳の異常を知るために医学的に開発された観測機器だが、これを用いて、人間の意識状態と脳の活動状態を関係づけることが出来るようになった。目を使っている時に活動しているところが視覚を司っている、などということが直接的に観測できるようになったわけで、この価値は大きい。解像度もかなり高いので、脳の活動状態と人間の意識を詳しく関係づけられる。
一方、MRIはMagnetic Resonance Imagingの略。脳の構造を外側から知ることが出来、また、観測時間が短いので人間の思考と脳の構造の関係を同時観測で知ることが出来る。例えば、人間と会話をしながら同時間観測で人間の脳の状態を観測するなどということ(機能的MRIと呼ばれる)さえ可能である。→ 詳しい原理
詳しい原理
PETの原理:
まず、脳の神経が活動時に消費する分子の一部の原子を放射性の原子で置き換えておく。この分子の溶液を血管に注射すると大脳に流れていって脳の活動が激しいところで集中的に消費される。放射性の原子なので脳の外側から発生する放射線を観測することにより、どこでこの分子が多く消費されているかを知ることが出来、従って脳のどこが活動状態にあるかということを直接知ることが出来るのである。
MRIの原理:
MRIでは体内に含まれる原子の原子核の位置と向きを磁気的に知ることが出来る。全ての原子は原子核とその回りをまわる電子で出来ており、原子核は陽子と中性子でできている。この内、陽子は小さい磁石になっており、磁場を用いて陽子の位置や運動の状態を知ることが出来る。実際には水素の原子核(=陽子そのもの)が測定対象である。人間の体は殆ど水でできているが水=H2O、つまり酸化水素であり、水素を含んでいる。したがって、MRIを用いれば体のどの部分でも測定することができる
これら二種類の方法の特徴は何れも「原子核」の性質を使っているということだ。人間の体内で起きているのは化学反応であり、原子核の反応である核反応は関係してない。この人体の機能とは無関係な原子核反応を利用することにより、人間の生体機能を妨害することなく、観測が可能になった。特に、大脳の様に神経の塊で神経の化学反応以外何も活動の無い器官の場合にはこの条件は大切である。勿論、PETやMRIは大脳以外の人間の器官の観測にも応用できることは言うまでもない。
権威ある研究者の参加
なんかこういうことを書くと「エライ人が注目するとみんながなびくなんて。科学に幻滅してしまう」とか思うかもしれないが、そういうことではない。過去にいい業績をあげた人が取り組んでいるということは、そのテーマにそれだけの価値があることを意味する。いい業績をあげた人は往々にしてテーマ選びがうまい人が多いからだ。もっとも、先駆者である津田教授の場合はそういうこととは無関係に研究をしていたわけだから本当にエライ研究者であれば大御所の動向に左右されずに研究が出来るのは間違い無いが。
で、意識の研究をはやらせた「権威ある研究者」とはクリックである。クリックはDNAの二重螺旋構造をワトソンとともに初めて解明した。現在、巷にあふれているカガク啓蒙書の多くが生物テーマで生命は大はやりだが、このブームももとをたどればワトソン・クリックのDNAの二重螺旋構造の発見に行き着く。それほど偉大な研究者だ。
ただ、クリック自身の意識の研究に対する貢献は今のところ「意識の研究も科学足りうる」ということを権威ある研究者たる自分が意識を研究して見せることで示した、という程度であり、画期的な成果を上げるには至っていない。まあ、こういうわけの解らない「意識」の研究を功なり名とげた科学者がやる、というだけでも十分えらいとは思うが。
従来の科学の研究手法
従来の科学の研究手法では、ある実験対象があったら、それにある操作を施して結果を比較対照することにより、その実験対照の挙動を明らかにする、というやり方をとる。例えば、あるバネがあり、その強さを調べたい、と思ったら、バネにいろいろな大きさの力を加えて伸び具合を測定し、「バネの強さ」を決めるわけだ。そこには暗黙の了解があって、「同じ力を加えればバネの伸びはいつも同じ」ということが仮定されている。同じ力を加えても違う伸び、などということは無い。勿論、仮定が誤っていればこの限りではなくて、例えば、占星術の様に「星の配置が人間の人生を決定している」ということを「科学的」に証明しようとしても、そもそも因果関係が無いのだから出来ないわけだ。
これに対して「意識」を「大脳の機能」として研究しよう、という場合には、「大脳の状態が同じなら同じ意識状態である」ということは一応、確実である。従って、そこには厳然たる因果関係はあるので科学の対象に十分なりうるわけだ。ところが、バネと違って大脳は大変複雑なので、外界からの刺激が無くても、活動を停止したりはしないわけで、早い話し、真っ暗で音もなく、味覚と触覚が麻痺した状態であったとしても(更に身体の全ての感覚がマヒしていたとしても)意識はすぐに無くなったりはしないだろう。大脳とはいわば、「力を加えなくても勝手に伸びたり縮んだりするバネ」の様なものなのだ。これでは「バネの強さ」なんて絶対測れない。そういう意味で大脳には従来の伝統的な科学研究の手法が全くと言っていいほど通用しないのだ。
「力を加えなくても勝手に伸びたり縮んだりするバネ」
例えば、嗅覚の情報処理を例にとってみよう。人間はにおいをかぎ分けられるのだから、においを区別する作業を脳のどこかで行っているはずである。ところが、驚いたことに、脳はおろか、人間の鼻の中にある臭いを検出する器官の神経の反応さえにおいと一対一対応が無いことが解っている。つまり、全く同じにおいをかがせても嗅覚器の反応が異なるのだ。まさに、「同じ力を加えても伸びの違うバネ」になってしまっており、 古典的な脳の情報処理観を真っ向から否定することになった。これは大脳から嗅覚器に フィードバックがあるためだと考えられている。
古典的な脳の情報処理観
例えば、視覚の情報処理の場合は次の様になっていると考えられていた。まず、網膜に写った像を視神経が信号に直す。この信号を、まず、第一段の神経回路が処理して大まかな要素(丸い、四角い、赤い、大きい、など)を取り出し、そのデータを次の神経回路網に送る。次の神経回路網では要素の相互関係が調べられ、次に両目からのデータを総合して奥行きをつけ....というように順々に処理されていくと思われていた。これなら、同じ物を見せれば少なくとも途中の段階までは視覚に関する神経回路網は同じ状態になるはずであり、実際、この機構を最初に見つけたグループはノーベル賞を授賞した。しかし、今から思えば、このような「きれいな」仕組みは大脳の情報処理機構としてはむしろ例外だったのだということが解る。
フィードバック
平たく言えば、梅干しを思い浮かべながらバラの匂いを嗅ぐのと、恋人を思い浮かべながらバラの匂いを嗅ぐのでは、嗅覚器官の反応からして違う、ということだ。「そんなんじゃバラの匂い、というものを一般的に認識することが出来ないではないか」と思うかもしれないが、それは、あまりにも人間が作る「機械設計」の思想に毒された考え方だ。確かに、人間が作る機械に同じことをさせようと思ったら、匂い検知のセンサーの出力を計算機に送って...というやり方をとるだろうが、だからと言ってそういうやり方以外は決してうまく行かない、というのはいい過ぎである。現実に人間の嗅覚がそれでバラの匂い、を知覚している以上、うまく機能していると思ってその理由を改めて考えなおすのが正しい態度だ。逆に言うと、そういう「機械設計の思想に毒された研究態度」みたいなものが大脳の研究を遅らせてきたともいえる。深く考えなければ、同じ匂いを嗅がせているのに違うシグナルが得られれば何か観測のやり方が間違っていると思うのが普通だろう。そういう意味では「嗅覚は匂いと一対一の対応が無い」ということを証明して見せたグループ(フリーマン教授、USA)があったということは実にすごいことだと言えよう。
意識の定義が不明解
勿論、どんな物だって、科学のレベルが低いうちは定義が不明解である。例えば、「星」という言葉を考えてみよう。天文学があまり発達していない時代には「星」というのは「夜空に輝く光点」という以上の何者でもない。従って、その当時「月」や「太陽」、まして地球自身を「星」と呼んだら「頭がおかしい」ということになっただろう。しかし、現代の我々は月も太陽も地球も月であることを知っている。そういう意味では、「定義」というのは科学の進歩とともにどんどん変わっていくものであり、それが自然である。
で、「意識」の科学的定義はどのくらいのレベルにあるだろうか?「星」の原始的な定義は間違っていたわけだが、それでも、人々が当初「星」と呼んでいたものはやっぱり今でも「星」なわけで、科学の進歩とともに「星」の定義が変化したと言っても、まあ、改良された、という程度である。これに対して、「意識」の定義の方はかなりお寒い状況である。はっきり言って「星」の場合の「夜空に輝く光点」という程度に衆目の一致する定義さえない状況である。
例えば、クリックによる「意識」の定義は「注意」である。
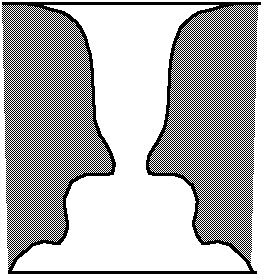
この図は何に見えるだろうか?壺?それとも向き合った顔?正直に言ってどっちとも見える、と言うのが本当だろう。しかし、目から脳に入ってくる刺激は同じなのである。にもかかわらず、壺に見えたり、顔に見えたりする。この「同じ刺激を二通りに解釈する」という能力は人間が何に注意を払うか(顔だと思うか、壺だと思うか)に依存している。この「注意」という能力が意識の本質である、と、クリックはみなした。確かに、「注意」という能力は人間の意識の非常に大事な部分だろう。だが、例えば、全ての感覚を絶たれ「注意」を払うものが無くなってしまったとしても意識は存在するだろう。そう考えると、「注意」という要素だけで、意識を定義するのは無理があるのではなかろうか。
現在のところ、意識のちゃんとした定義は存在しない。というより、そういう「万人が納得する定義」のような物を作るのは無理だろう。むしろ、「これが意識である」という定義を作り上げて、それについて徹底的に研究をする、という態度が必要とされるだろう。いかに、その定義が不完全に見えても。
できないことはできない
計算機は定義されたことしか出来ない。だから、その辺で売っている電卓には必ず「エラー」の表示がついていて、出来ない計算を要求されると(1をゼロで割れ、とか)「エラー」を出すことになっている。その点、どんなに大きな計算機であっても、基本的には同じことである。計算機には必ず「実行打ち切り」の機能がついていて、プログラムに重大なバグがあれば、停止することになっている。このイメージがついてまわるためか、古今東西のSFでは人知を越えたコンピュータやロボットを人間が打ち倒すのに人間にはどうってことはないが、機械には乗り越えるのが困難なジレンマを与えて回路を暴走させる、 というやり方を使う話しがくり返し出てくる。
というやり方
アシモフのロボットものにもその手のテーマの短編が出てくる。ある偶然で人間の心を読んでしまうロボットが出来てしまう。このロボットにわざとある人の心からその人が人に知られたくないと思っていることを読み取らせる。そして、その人がロボットに本当のことを言うように命令する。ロボットは本当のことを言えばその人を傷つけ、また、嘘を言えば、その人の命令に背くことでやはり、その人の心を傷つける。「人を傷つけてはいけない」とプログラムされているそのロボットはいずれの行動も取れなくなり、壊れてしまう、というものである。
人間なら何とかしてしまう
この例など人間の日常ではざらであり、その度に機能を停止していたのでは、人間の数がいくらあっても足らないだろう。つまり、人間の本質はジレンマがあってもとにかく行動を決定できる、という点である。最悪の場合は、「わかりません」で済まされる。こういう機能は全て論理だけで組み立てられた計算機のプログラムには決して持つことが出来ない。この「矛盾があっても行動できる」という機能こそ人間の大脳のみにあり、計算機が欠いている機能である。
この計算機が欠いている部分こそ「意識」の部分なのである。
チェスの世界チャンピオンに勝てる計算機
この2月にIBMのスーパー計算機上で動くチェスプログラムDeep Blueはついに人間のチェス世界チャンピオン、32歳のKarpanovを打ち破るという快挙を成し遂げた。これは現実のチェスルール(対戦方式)において人間のチャンピオンに計算機が初めて勝ったということを意味する。勿論、チェスはゲームに過ぎないが、それでも、複雑な思考、に関する限り、計算機は着々と人間に近づいている。
「意識」をつくるアルゴリズム
意識とは外界からの刺激と刺激を処理する大脳の中間に位置し、都合の良いものだけ取り出すフィルターのようなものだと書いた。これはまた、別の言い方をすれば意識は「大脳」という自己と「刺激」という外界を両方とも検知出来るということになる。これは実は非常にややこしいことをもたらす事になる。何がややこしいかというと、大脳もまた、物質には違いないから、意識にとっての「外界」の中には「大脳」自身も含まれる。ところが、意識、という機能自体は大脳の機能に過ぎない(と、思っているのだが)のであるから、意識は意識自身を意識するということになる。ところが、その意識が意識している意識の中には意識が含まれているので、その意識をまた意識する意識を意識しなくてはならず....、段々頭が痛くなってきたが、要するに、意識は意識という自分自身を意識する、という入れ子構造を持っている、と言う事になる。ちょうど 合わせ鏡や、モニターをカメラで写してその出力をまたモニターに流す、という作業に等しい構造を持ち、自分自身の中に自分自身のコピーを無限個持っていることになる。
この入れ子構造を大脳はどうやって実現しているのだろうか。人間の思考は基本的には計算機と同じで論理的であり、物事を「真実」と「虚偽」に分けなくてはならない。しかし、計算機の様に「真か偽か」という「二者択一」の回路を生物である人間が持つことは出来ないので、これを化学反応の式で表現しなくてはならない。化学反応の式に出てくるのは「物質の濃度」という連続な量であり、「二者択一」の量ではない。そこで、「真と偽」とい二つの状態の中間の状態も取れるように考えて回路を組んで計算することにより、大脳の動きを模倣することが出来る。
この様にして作られた回路の中に意識特有の入れ子構造を導入してやると自然に カオスが出現する。ちょうど、 モニターをカメラで写してその出力をまたモニターに流す時にカオスが現われる様に。つまり、大脳の中にはカオスがなくてはいけない。そして、これは実際に観測されている。人間の頭脳、という高度に論理的で知性的であるべき存在にカオスが存在するのは一見、奇妙に思えるが、実際には意識特有の「入れ子構造」の必然的な結果なのである。この「大脳はカオスで動いている」という考え方は津田教授の先駆的な著書「カオス的脳観」(サイエンス社 1990)に詳しく述べられている。興味ある方はお読みいただきたい。
合わせ鏡
鏡を二枚向かい合わせてその間に立てば鏡に写った鏡の中にまた鏡があることになり、無限枚の鏡が見え、その無限枚の鏡の一枚一枚に自分が写っているので無限個の自分の像を見ることになる。意識はちょうどこれと同じ様な境遇に置かれているわけだ。
モニターをカメラで写してその出力をまたモニターに流す
こんなことをしても何も起きない、と思うかもしれないがさにあらず、奇妙な模様を見ることになる。この模様は往々にしてカオスを産み出すことになる。暇があったらやってみていただきたい。これはちょうど、スピーカーとマイクを近づけすぎた時に起きる耳をつんざく騒音、いわゆるハウリングの映像版である。ハウリングでは、マイクに入ったごく些細な音が、増幅されてスピーカーから出力されそれがマイクに拾われてまた増幅され、という課程を経て、最初の小さな音とは似ても似つかない刺激音を作り出す。これは、マイクとスピーカーによる音の増幅が不完全であるためだ(マイクを通せば多かれ少なかれ声は変わるだろう。)非常に些細な不完全性だから通常は問題にもならないが、マイク→スピーカー→マイク→スピーカー.....と言うように入れ子構造で無限回繰り返した場合には致命的な効果を産み出し、とんでもない音を作り出す。「意識自身を意識する意識」もまたこのような危険な構造を持っている。意識自身がフィルターの役目をして無意識に不必要な部分を捨てさる、という作業は、マイクの入力がスピーカーに出力される前の部分にノイズを除去する回路をつけてハウリングを防ぐようなものである。意識というフィルター、無意識というゴミ捨て場がなければ人間の頭脳はハウリングを起こしたスピーカーの様にたちまちにして狂ってしまうだろう。
カオス
1995年5月号の本コラムでも登場したカオスという言葉をおぼえておられるだろうか?ここでは、カオスの別の面を紹介しよう。月は地球の回りを、地球は太陽の回りを、規則正しくまわっている。一年経てば必ず同じ速度で同じ場所を通過する。これは太陽系内の全ての星について成り立っていてだからこそ、ハレー彗星は正確に78年毎に地球を訪れるわけだ。これはカオスではない。もし、星の運行がカオスであれば、星は同じ場所に一定の時間でもどって来ることは決してない。それどころか、同じ場所に戻ってくるまでの時間はいつも違っていて、二度と同じ時間間隔で戻ってくることはあり得ない。つまり、カオスは完全に不規則なのだ。ビデオカメラとモニターでうまくカオスが作れれば、そこに現われるも様は千変万化で決して同じ物が繰り返されないのを見ることが出来る。
�
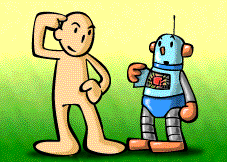 意識、というのは一体、何だろうか。人間にとって「意識」が一番大事だと皆思っているのではないだろうか。どんなに何かの能力が高い人間がいても「意識」を持っていなかったら、人間とは呼べないだろう。それは チェスの世界チャンピオンに勝てる計算機とか、絵画を創作できるコンピュータの様な「装置」に過ぎない。人間が人間たる最低限の条件は「意識」を持っていることだと思われている。
意識、というのは一体、何だろうか。人間にとって「意識」が一番大事だと皆思っているのではないだろうか。どんなに何かの能力が高い人間がいても「意識」を持っていなかったら、人間とは呼べないだろう。それは チェスの世界チャンピオンに勝てる計算機とか、絵画を創作できるコンピュータの様な「装置」に過ぎない。人間が人間たる最低限の条件は「意識」を持っていることだと思われている。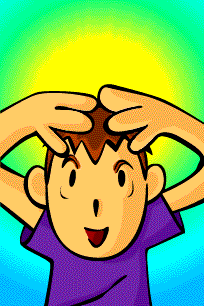 この様な行き方、つまり、「意識とは大脳と言う器官の機能の一つである」という考え方が主流になってきた背景は2つある。その第一は、 測定技術の進歩であり、また、もう一つは 権威ある研究者の参加である。そのおかげで、「意識」を研究すること自体は非常にメジャーな研究となったがその成果自体はお寒い限りだ。
この様な行き方、つまり、「意識とは大脳と言う器官の機能の一つである」という考え方が主流になってきた背景は2つある。その第一は、 測定技術の進歩であり、また、もう一つは 権威ある研究者の参加である。そのおかげで、「意識」を研究すること自体は非常にメジャーな研究となったがその成果自体はお寒い限りだ。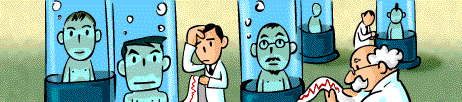
 計算機と人間の差は柔軟性にある。計算機は
計算機と人間の差は柔軟性にある。計算機は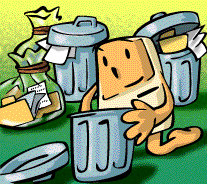
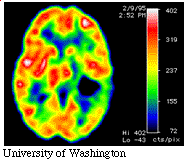 PETはPositron Emission Tomographyの略。これを使うと脳のどの部分が活動しているかを知ることが出来る。もともとは医学的に脳の異常を知るために医学的に開発された観測機器だが、これを用いて、人間の意識状態と脳の活動状態を関係づけることが出来るようになった。目を使っている時に活動しているところが視覚を司っている、などということが直接的に観測できるようになったわけで、この価値は大きい。解像度もかなり高いので、脳の活動状態と人間の意識を詳しく関係づけられる。
PETはPositron Emission Tomographyの略。これを使うと脳のどの部分が活動しているかを知ることが出来る。もともとは医学的に脳の異常を知るために医学的に開発された観測機器だが、これを用いて、人間の意識状態と脳の活動状態を関係づけることが出来るようになった。目を使っている時に活動しているところが視覚を司っている、などということが直接的に観測できるようになったわけで、この価値は大きい。解像度もかなり高いので、脳の活動状態と人間の意識を詳しく関係づけられる。